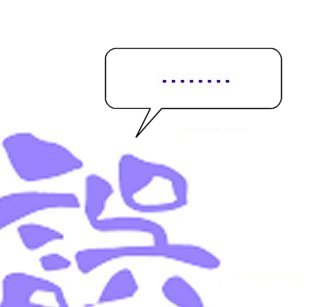verschlungen und verschmolzen /
試訳:くんずほぐれつ
手っ取り早く外国語を学ぶにはポルノを読むといい、と最初に言ったのは誰だろうか。けだし至言だ。ご家庭にヴィデオが普及したのもレンタルショップにアダルト・コーナーが常設されているからだしー(をひ
いやね……ヘフト通販のカタログをながめてると、やっぱりそーゆーコーナーにも目がいくわけで(笑)
洋の東西を問わずというか、「名作もの」が並んでたりして。『ガリベラ』とか『ピノッキア』とか。なぜに女性形。これが男なら、ウソをつくとアソコがぐんぐんと(爆)
残念ながらまだ実物を拝んだことはないのだが。たぶん、スラングとかそっち系のボキャとかいっぱいで手も足も出ないと思うんだけどね。実際、はじめて『ミュトール』や『ジョン・シンクレア』を読んだときは、ファンタジー系やホラー系の用語がわからず四苦八苦したもの。そりゃポルノにも当然あるはず。局部描写とか(笑)
まあ、それはそれで新たな境地が拓けるかもしれない……って単に欲望に忠実なだけじゃん。
ちなみに、用例は『ソラー・ステーション』冒頭、宇宙ステーションのリネン室で新たな境地の開拓にいそしむ主人公レナードとヒロイン美子さんの一幕から。「地上400キロを周回しながらこの美しいけものと絡みあい融けあうのだ。」という文章だが、下世話に訳そうとすると、こんなんかなー、と。
■原典:アンドレアス・エシュバッハ『ソラー・ステーション』