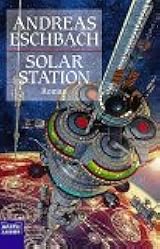ハヤカワ版:(p143)
三四五六年、太陽系帝国はなお混乱していた。大群に勝利してから、十四年が経過しようとしているにもかかわらず。それでも、太陽系人類は活力をとりもどしたほうなのだ。銀河のほかの宙域では、依然として大群の傷跡がのこされていた。テラニア政府から離脱した植民者の星間国家は、ほぼ崩壊状態にある……新アルコン人の国家群や、アコン帝国も同様だ。こうした国家がいつ安定をとりもどすか、だれにも予想がつかない。したがって、国内がある程度まで安定した太陽系帝国……太陽系人類は他種族に対し、圧倒的に優位な立場にある。銀河所属の同盟関係は、はるか過去のものとなったのである。
先見性のない者は、この運命の恩恵を認めようとせず、さらなる発展に利用する権利を放棄せよと叫んだ。しかし、ペリー・ローダンは近視眼的判断をくだす人間ではない。大執政官たる者、太陽系人類の福祉を第一に考え、あらゆる手段をつくしてそれを実現しなければならないのだ。太陽系帝国が銀河諸種族の頂点に立っている以上、大執政官には、原生人類の膨張願望を満足させる必要があった。さらには、他種族に先んじる願望も。
原文:
Das Solare Imperium des Jahres 3456 hatte die Wirren, in die es durch das Auftauchen des Schwarms vierzehn Jahre zuvor gestürzt worden war, überwunden. Dieser Umstand allein sprach für die Tatkraft und die Entschlossenheit des Erdenmenschen; denn in anderen Gegenden der Galaxis waren die Folgen des Schwarms noch immer deutlich zu spüren. Selbst solche Sternenreiche, die von terranischen Auswanderern gegründet worden waren, sich jedoch frühzeitig von der Bevormundung, wie sie es nannten, der Regierung in Terrania City losgesagt hatten, befanden sich immer noch im Zustand der Desorganisation – ebenso wie die neu-arkonidischen Staatsgebilde und das Reich der Akonen. Zwar war überall vorauszusehen, dass man eines Tages in nicht allzu ferner Zukunft den Zustand der Stabilität wieder erreichen würde. Aber innerhalb des Solaren Imperiums war das Gleichgewicht schon jetzt wiederhergestellt, und die terranische Menschheit befand sich damit den anderen Völkern der Galaxis gegenüber in einer Vorrangstellung, wie sie sie seit den längst vergangenen Tagen der Galaktischen Allianz nicht mehr innegehabt hatte.
Kurzsichtig wäre derjenige gewesen, der die Gunst des Schicksals nicht erkannt und darauf verzichtet hätte, diesen Vorteil zu nutzen und weiter auszubauen. Niemand aber hatte Perry Rhodan je kurzsichtig nennen können. Die erste Sorge des Großadministrators galt dem Wohl der solaren Menschheit, und auf keine Weise ließ sich diesem Wohl besser dienen als dadurch, dass er die Vorrangstellung des Imperiums unter den Völkern der Milchstraße stärkte und dafür sorgte, dass die Einflusssphäre des irdischen Menschen vor den Expansions- und Eroberungsgelüsten anderer Sternnationen sicher war.
試訳:
三四五六年の太陽系帝国は、十四年前に大群の出現によって突き落とされた混乱を克服していた。この状況だけでも地球人類の活力と意志力を端的にあらわしている。銀河の他の宙域では、大群の後遺症が依然克明に残されているのだから。テラからの移住者によって建設され、かれらの言う「テラニア政府の干渉から早期に解放された」星間帝国ですら、いまだに無秩序状態にあった――新アルコン人の国家群やアコン帝国と同様に。そう遠くない将来に安定した状況までたどりつく兆候は、確かにそこかしこに見られた。だが、太陽系帝国の内部は現在すでにバランスをとりもどしているのだ。つまり、テラ人類は銀河の他種族に対するアドバンテージを占めたということ。これは、はるか過去のものとなった銀河同盟の時代から、たえてなかったことだ。
この運命の恩寵を見落として、与えられた利点を活用することを怠るなら、先見に欠けるというもの。だが、ペリー・ローダンを近視眼的とそしる者はいまい。大執政官の関心はまず第一に太陽系人類の福祉にむけられており、それにあたっては、銀河諸種族の中における帝国の優位をいっそう強化し、他の星間国家の拡張志向や征服欲から地球人類の影響圏を安んじせしめる以上の良策はありえなかった。
原典:300巻『太陽系帝国の守護者』後半
※2019/06/26 ハヤカワ版抜粋および原文を追加