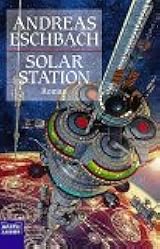先日紹介した、東京創元社の21世紀東欧SF・ファンタスチカ傑作集『時間はだれも待ってくれない』が、昨日発売となった。
見本は一昨日手元に届いていたし、昨日、東京日本橋丸善でも入荷を確認済なので、公式でも一部「30日発売」のままとなっているが、オフィシャルな発売日は昨日29日でいいはず。平積みになるような本でもないし、たぶん、それほど発行部数は多くないと思われるので、興味がおありの向きは、発見次第保護されるのがよろしかろう。でもって感想等聞かせていただけると倍うれしい(わたしが)。
四六判300pは、手に取ると意外とこぢんまりしている。実際には去年の春に原稿を渡して以来、わたしはほとんどなんにもしていないので(笑)、むしろ『インターネット~』の同人が刷り上がったときの方が達成感はあったような……(をひ
ともあれ、これで一区切りである。話が動き始めてから、間に大震災が起きたりして、刊行があやぶまれた時期もあった。編集サイドの苦労は想像を絶する。そもそも、訳者・解説者だけで10名超、著者や版元まで含めるといったいどのくらいの人数が関わったのか。それらをとりまとめた編者・高野氏と担当・K氏には、お疲れ様、と申しあげたい。
#おふたりには、まだこれから「ロシア編」の作業が待っているわけだが。
公式にも掲載されているが、収録作品は以下のとおり:
- 「ハーベムス・パーパム(新教皇万歳)」モンマース(オーストリア)
- 「私と犬」フランツ
- 「女性成功者」ブルンチェアヌ(以上ルーマニア)
- 「ブリャハ」フェダレンカ(ベラルーシ)
- 「もうひとつの街」アイヴァス(チェコ)
- 「三つの色」フスリツァ
- 「カウントダウン」フスリツァ(以上スロヴァキア)
- 「時間はだれも待ってくれない」ストゥドニャレク(ポーランド)
- 「労働者階級の手にあるインターネット」シュタインミュラー(旧東ドイツ)
- 「盛雲(シェンユン)、庭園に隠れる者」ラースロー(ハンガリー)
- 「アスコルディーネの愛─ダウガワ河幻想─」エインフェルズ(ラトヴィア)
- 「列車」ジヴコヴィッチ(セルビア)
残念ながらまだアタマの方しか読めていないので、内容については、またいずれ。
自分の担当分で誤植とか発見してしまった(たぶん、わたしのせい)ので、そのへんも合わせてorz
■東京創元社:時間はだれも待ってくれない
■前回の記事:新・東欧SF傑作集(仮)つーから、文庫とばかり…