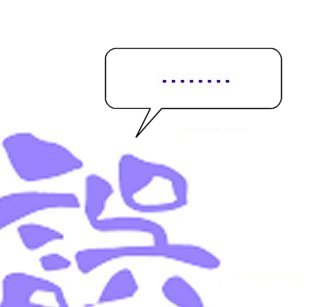ローダンの姉妹シリーズATLANは1969年に正篇と同じヘフト形式の月イチ(正確には4週ごとに1話)刊行でスタート。1年後に隔週刊、1978年には週刊と刊行ペースを上げるが、1988年、850話をもって終了した。
ローダンの姉妹シリーズATLANは1969年に正篇と同じヘフト形式の月イチ(正確には4週ごとに1話)刊行でスタート。1年後に隔週刊、1978年には週刊と刊行ペースを上げるが、1988年、850話をもって終了した。
その後、1998年にロベルト・フェルトホフ草案の独立した〈トラヴェルサン・サイクル〉全12話が週刊で刊行され好評を博したのを契機に、2003年にケンタウリ・サイクル全12話が、さらに2004年のオブシディアン・サイクルからは「新ATLANヘフト」として通し番号が振られるようになり、2006年の炎塵サイクルで完結するまで全60話が刊行された。
現在Perrypediaでは各12話の7つのサイクルを「ATLANミニシリーズ」に分類しているが、個人的にはひっくるめて「新ATLANヘフト」と呼んでいる。
現在の正篇、3200話からのフラグメント・サイクルでは、「850年前にアトランがグルエルフィン銀河を訪れた」ことが語られるが、それを含め、正篇に影響を及ぼす設定等もあるので、おおまかなストーリーの流れを概括してみた。
1 トラヴェルサン / Traversan
新銀河暦1290年、惑星トラヴェルサンで島の王の遺産が発見され、急報をうけて駆けつけたアトランが島の王と誤認されたため、時間ステーションの秘密プログラム〈星の露〉が発動。アトランは紀元前5772年に移送されてしまう。現地領主の娘タマレナとねんごろになったアトランは、トラヴェルサンの人々とともに悪逆非道の星区総督の陰謀に立ち向かう。
正篇1900話台で、ギャラクティカム議場を「ちとヤボ用で」と中座してトラヴェルサンへ向かうシーンがある。次に登場するまでに1万年が経過しているとは誰も思うまい(笑)
草案:ロベルト・フェルトホフ
2 ケンタウリ / Centauri
 正確にはオメガ・ケンタウリ(球状星団ケンタウルス座ω)。
正確にはオメガ・ケンタウリ(球状星団ケンタウルス座ω)。
新銀河暦1225年、アトランは建国まもないアルコン水晶帝国において、レムール人の遺産をめぐる陰謀にまきこまれる。ケンタウルス座ω星団に眠る恒星転送機と意識転送技術を先んじて見出したツォルトラル家当主クレスト=ターロ、そしてコスモクラートのロボット、サムカーもからんで錯綜した事態のいきつく先は――。
この頃は、まだ別れた恋人でもある女帝シータさんが健在なので、アトランも帝国内で比較的自由に行動できた。この事件で発見されたω星団中心部の恒星転送機〈カラグ恒星十二面体〉は、後の正篇、ハイパーインピーダンス上昇により超光速航行技術の衰退した状況で、銀河間移動のための恒星転送機網再稼働の中心的役割を担い、長らく活躍する。
草案:ウーヴェ・アントン
3 オブシディアン / Obsidian
カラグ恒星転送機の事故で、未知の空間〈オブシディアン・ギャップ〉へはじきとばされたアトラン。それは5億年以上昔に、あまたの宇宙に於いて活動した原初の〈大群〉リトラクドゥールムのバックアップ・システムの座。そして、ヴァルガン人女性キサラの協力もあり、アルコン人はω星団が混沌勢力の攻撃で銀河系に擱座したリトラクドゥールムの一部であったことを知る。そして、100万年前銀河系に残留したサイノスのひとり、旧知の山師カリオストロことサルダエンガルが、銀河系を犠牲にリトラクドゥールムの再起動をもくろんでいることを。
ヴァルガン人はATLANシリーズにおけるサイノスやクエリオン人的位置づけの種族で、七強者の城で出てきたマイクロ宇宙との往来を可能とするドルグン転換器を開発した種族の末裔。若き日のアトランはその叛徒の女王、〈黄金の女神〉イシュタルと出会い、一子カパトをもうけている。
4 大法官 / Die Lordrichter
カラグ恒星転送機の制御惑星カラグ鋼鉄界に出現したカピンから、〈ガルブの大法官〉と〈秩序の剣〉について警告をうけたアトラン。キサラとともに、銀河系のサウスサイドに遺されたヴァルガン人の施設で、その尖兵が活動していることをつかむ。〈プシの泉〉ムルロースの破壊には成功したが、すでに回収されたエネルギーは〈ダークスター〉と呼ばれるプロジェクトのため、1600万光年かなたのドゥインゲロー銀河へ移送されていた。
ガルブヨル――ガルベッシュを連想させる――は現在グルエルフィンに侵攻し、カピンに血みどろの内戦をひきおこしているという。
5 ダークスター / Der Dunkelstern
マイクロ宇宙からの暗黒物質に侵された恒星〈ダークスター〉。不死性を求める大法官の〈突破計画〉を阻止するべくドゥインゲロー銀河に進撃したアトランとキサラは、現地のヴァルガン人やカピンの協力を得て、ダークスターの破壊に成功する。
6 イントラワールド / Intrawelt
ドゥインゲロー銀河に構築された直径30万キロの人工空洞惑星イントラワールド。ガルブヨルの叛乱勢力コンタークラフトによれば、そこに隠された〈炎塵〉があれば戦局を好転させうるらしいが、空洞惑星には「物質の泉の彼岸に到達した」者しか立ち入れないという。アトランはキサラを残し、単身イントラワールドへ進入する。
先んじて空洞世界に来訪していた、かつてカオタークの協力者であった〈ソウルイーター〉ペオヌとの競争を制し、アルコン人は謎に満ちた〈炎塵〉を確保する。
ペオヌはカオターク・クズポミュルが蠱毒のように養成したソウルイーターであり、《トレーガー(母艦)》と呼ばれる特殊艦で活動する特殊部隊〈チャンピオン〉の一員だった。チャンピオンは2000話以降の正篇にも2名ほど登場する。また、ヘクサメロンの主ヘプタメルに力を与えたのもクズポミュルである(ただしこの設定は惑星小説のみで正篇には出てこない)。
草案:ミハエル・マルクス・ターナー
7 炎塵 / Flammenstaub
炎塵は服用者に現実改変能力を与える。だがそれは諸刃の剣であり、使いこなせなければ死をもたらすもの。自分にその力は余るとアトランは銀河系への戦略的撤退をはかるが、ガンヤスのペドパイラー船はグルエルフィン銀河を目的地に選んでしまう。
ガンヤス人とタケル人の会戦にまきこまれたアルコン人は、介入したジュクラ人に救出される。ジュクラ氏族を糾合する会合はガルブの親衛隊ザコールとタケル人によって粉砕されるが、会場を脱出したアトランらは山脈に隠された〈家臣〉を発見、脱出した先の自由貿易区の中心ボイシュ・ステーションで瀕死の言葉を伝える者から〈永遠のガンヨ〉オヴァロンの意識片を受け入れる。
ガルブヨルはガルベッシュと同じくトロダル――勇猛に戦いぬいた戦士のみがたどりつける死後の世界――を信奉するヴァンカナル銀河の戦士種族集団。14名の大法官と最高大法官、そして頂点に立つ〈秩序の剣〉に率いられる。だが、当代の〈秩序の剣〉エミオンは、実は異なる蓋然性平面からの来訪者で、苦痛でしかないこの宇宙での生を終わらせる手段を求めていた。
海星船《フム》での最終決戦でエミオンが異なる存在平面へ放逐された後、新たに〈秩序の剣〉に就任した大法官、タケル人サリラはオヴァロンの意識片を受け入れ、ガルブヨルのヴァンカナル銀河への撤退を開始した。
……本編ではなく、Perrypedia収録のあらすじをざっと眺めただけだが、それだけでも〈永遠のガンヨ〉あたりに誤解のあったことが判明した。
正篇3200話で付帯脳が「前に来たのは800年以上前のこと」とつっこみを入れるのが、最後の炎塵サイクルの事件(新銀河暦1225年)である。ただし、これだけ見ても、正篇1277話で成立したグルエルフィン同盟がどうなったかはっきりしない。インタプリタ(と書くと、某コンパイラを思い出してしまうなw)が出てくるので、15年前に内戦が勃発するまでは基本構造は似通っていたものと想像される。
正篇でパンヤス人のトップが〈永遠のガンヤ〉(ガンヨの女性形)なのは、オヴァロン崇拝が廃れたのか、シラリアの後継たるガンヨが下克上したのかも不明。このへんはおいおい明らかになると思われるが、どうかなあ。
■Perrypedia:ATLAN-Miniserien