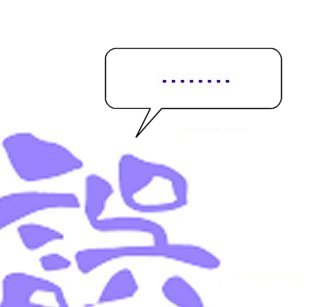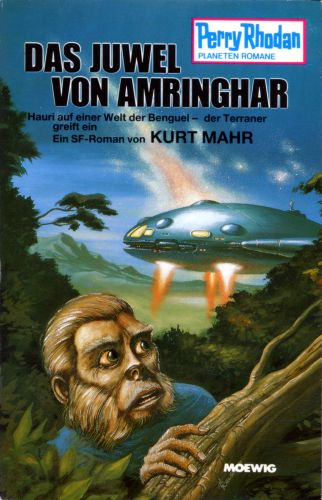1000話「テラナー」について、第5回である。
ごやてんでもこそっとリンクを貼ってあるが、William Voltz のウェブサイトがある。
ローダン関連のサイトができたのは90年代後半からなので、無論、フォルツ自身が関与しているわけではない。2004年にドイツ語圏SFの後進育成のためとして、短編の名手でもあったフォルツの名を冠した賞(William Voltz Award)がつくられた、そのサイトである。
(→ フォルツ賞、応募・投票受付中)
※2004年第1回開催時の記事である。
フォルツ賞自体は、2009年の第5回以降休止状態となっているが、おそらくフォルツと交友関係があり、初期の審査を務めたヴルチェクが亡くなった(2008年)こととも無関係ではないだろう。
しかし、その後もサイトは地味に更新を続けている。フォルツ未亡人であるインゲ夫人による、フォルツのバイオグラフィーである。
第4部 そして新たな歯車は回る
最新の39回は、1074話のシェール復帰話と、慢性的な気管支炎をかかえたフォルツがインゲさんの懇願によってようやく医者にいき、抗生物質を処方されたあたりで終わっており、続きを読むのがちょっとこわい……のはさておいて。
このバイオグラフィーを読むと、シェールとフォルツの師弟関係が、シリーズのごく初期からのものであったことがよくわかる。1962年に購入したオペルの中古車で、オッフェンバッハから20キロほどの距離にあるフリードリヒスドルフのシェール宅へ、まだ婚約時代のインゲさんをともなって、フォルツは足しげく通っていたそうな。
アイデアをメモって来いとか、今後のシリーズの展開はあーもあろこーもあろと、2人して夢中で論議する姿をインゲさんはおぼえていた。実際シェールによって構築された世界観のどの程度がフォルツの提出したアイデアに影響されたものなのかはわからない。ただ、これまでは漠然と、大戦の従軍経験があるシェールやダールトンの生み出したローダン・シリーズと、兵役を忌避した(実際はハネられた)フォルツの考案する宇宙とは、異なるものであって当然と考えていたのだが、そのへん改める必要もあるだろう。
さて、カルフェシュとグッキーの後押しにより、機能をとりもどしたライレの目で、現在の〈それ〉の中央惑星エデンIIへの無間歩を果たしたペリー・ローダン。
しかし、新たな超知性体の座たる半球惑星は、思いもよらない様相を呈していた。
……戦いの準備である。
◆
ハヤカワ版(p249):
砂によってプラスティックのようにつるつるに磨きあげられた、岩の上に立っているようだ。
原文:
Das Material, auf dem er stand, konnte ebenso gut glattgeschliffener Fels wie Kunststoff sein.
試訳:
足下の素材は、磨きあげられた岩とも合成素材ともとれた。
ebenso gut A wie B で、Aと同じくらいB。なのでこの場合、岩と合成素材、どちらも同じくらいにありそうだ、となる。
ちなみに元々この文章は、ebensogut glattgeschliffenener Fels wie Kunststoff と書かれていたものだが、1996年の表記法改正で ×ebensogut ○ebenso gut と決められたため、手元の第2版では ebensogut、電子書籍版が ebenso gut となっている。たぶん、ハヤカワ版は後者が底本で、ebenso 「(とっても)つるつる」 / gut glattseschliffenen 「よく磨きあげられた」と読んでしまったのではなかろうか。
ハヤカワ版(p250):
もう一度“目”をのぞいてみたが、やはり暗いままだ。
原文:
Er schüttelte das Auge, aber es blieb verschlossen.
試訳:
〈目〉を振ってもみたが、閉ざされたままだった。
ローダン、いろいろ試行錯誤してるのだ(笑)
翻訳する側としても、ぜひ彼の努力を汲みとってあげていただきたい。
ハヤカワ版:
目の前にグレイの物体の影が落ちた。ちいさな尖塔のような形状で、
原文:
Vor ihm schälte sich ein Schatten aus der grauen Substanz. Das Gebilde sah aus wie ein kleiner Obelisk,
試訳:
前方、灰色の霧のなかからひとつの物影があらわれた。小さなオベリスクのような物体で、
動詞 schälen は、後で出てくるたまねぎの“皮”と同根で、「皮をむく、(再帰動詞で)皮がむける」。グレイの物質とは、霧(私家版では“もや”)を構成するもので、そこから皮がむけるようにオベリスクの影が見えてきたのだ。
個人的に“影を落とす”は werfen Schatten 「影を投げかける」が該当すると思う。これはバルディオクがらみの記事ですでに書いた。
(→ 続々850話・影を投げかける誤訳)
上記のような混同が生じたのは、前置詞 aus に「~製の」という意味があるためだろうだが、困ったことにこれ以降、“グレイの”尖塔と本来ない描写がついたり、“グレイの物質”と書いてあるのに“尖塔”と訳したりしている。
ちなみに尖塔=オベリスクだが、サイノスがらみで後々まで頻出する語でもあるので、伏線である可能性を考慮すると揃えておいた方がよろしいのでわ。まあ今回は無関係だが。
ハヤカワ版:
その働きを知ろうとするのはむだだろう。ローダンはグレイの物体が配置された範囲をはるかにこえて存在する、目に見えない柱の内部にいるような印象をうけた。
原文:
Den Sinn dieser Anlage ergründen zu wollen war sicher ein wenig aussichtsreiches Unternehmen. Rhodan hatte den Eindruck, im Innern einer unsichtbaren Säule zu stehen, die weit aus dieser grauen Substanz irgendwohin reichte.
試訳:
この装置の意味を解明すれば、多少なりと展望が開けるかもしれない。自分が灰色の霧を抜けたどこかに通じる、見えざる柱の内部にいるようなイメージがあった。
ein wenig なので「ちょっとだけ」。wenigだけ(“ちっとも”)ならたしかに「無駄」だが。直訳すると「この施設の意味を解き明かそうと欲するのは、きっと少しは有望な計画だろう」くらいになるのかな。
そして上述したように、霧のことを“配置されたグレイの物体”≒尖塔と読んでいる。
ともあれ、見込みがある(aussichtsreich)から、この後ちょろっと考察してるわけだ。そして、その結果であるが……。
ハヤカワ版:
エデンIIをつつみこんでいる駆動装置の一部かもしれない。
そうだとしたら……どこに向かっているのだ?
原文:
Vielleicht waren sie Teil einer gigantischen, EDEN II umspannenden Transportanlage.
Wenn diese Vermutung richtig war – was wurde dann hier transportiert?
試訳:
あるいはエデンⅡを包括する搬送機構の一部かもしれなかった。
もしこの推測が正しいとしたら――何を運んでいる?
Transport である。Tran’Sport! なら佐川急便である。そしてローダンで駆動装置(エンジン)といえばだいたい Triebwerksystem か Antrieb だ。全然ちがう。
そもそも、仮にもおカネもらって翻訳している人が、wo「どこ」と was「なに」を読み違えるとも思えないのだけど。一行前にもどって訂正するのすらめんどくさいのかね……。
ハヤカワ版(p251):
突然、笑い声が聞こえた。だれかがこちらの推測をテレパシーで読みとり、あざけっているかのように。
原文:
Rhodan hörte plötzlich Gelächter, als hätte jemand seine Spekulationen telepathisch erfasst und würde sich darüber lustig machen.
試訳:
ふいに笑い声が聞こえた。まるで誰かがローダンの推量をテレパシーでとらえて興じているようだ。
形容詞 lustig は「愉快な、おもしろい、陽気な」。たしかに、手元の新現代独和辞典の用例でも sich über (IV格) lustig machen を「ちゃかす、からかう、(あざけって)おもしろがる」としているが、同ページ中ほどで登場したタコ・カクタが“さっき耳にしたのと同じ声で笑い”とあるので、嘲笑というよりはおもしろがっている意味合いに取らないと、旧友同士の再会は対面する以前に破綻してしまう。
ハヤカワ版:
なにが起きたのだろうと思い、もうすこし“なか”にいたかったと感じる。
原文:
Unwillkürlich fragte er sich, was mit ihm geschehen wäre, wenn er sich noch einige Augenblicke länger ≫in der Röhre≪ aufgehalten hätte.
試訳:
もうあと少しあの“パイプ”の中にとどまっていたら、いったいどうなったことか。
今回は書かずに済むかと思ったが……接続法第II式である。なのに「もし~だったら」の wenn がどこにも活かされていない。
試訳で“パイプ”とした Röhre は、3章でジンカー・ロオクが利用した非常用パイプ網と同じ語なのだが、そもそも搬送システムを駆動装置と誤訳しているので、パイプの中、という表現が前後と脈絡がつかなかったのだろう。こうやって、どんどん描写が削られていくわけだ。
ハヤカワ版(p252):
「エデンIIにようこそ、ペリー。ずっと待ちつづけていました」一瞬ためらい、声を落として先をつづける。「べつの姿を考えていましたが」
原文:
≫Willkommen auf EDEN II, Perry. Wir hatten dich eigentlich schon früher erwartet.≪ Er zögerte einen Augenblick und fügte dann leiser hinzu: ≫Und in anderer Form.≪
試訳:
「エデンIIへようこそ、ペリー。実際もっと早くおいでになるものと、われわれ、考えていたのですが」一瞬ためらってから、小声でつけたした。「もっと別の形で」
われわれ、とは後述されるように“昔の友たち全員”で、もっと別の形とは、「訪れては去っていく」客としてではなく、精神集合体の一部としてであることは、一連の流れから理解できる。にしても、わざわざわかりづらく訳すことはあるまいに。
ハヤカワ版:
「わたしに意識集合体にくわわれ、と……そういっているのか?」そうたずねた瞬間、強制的に統合するつもりなのかという思いが頭をよぎった。
原文:
≫Wird man mich … animieren, in das Bewusstseinskollektiv einzutreten?≪, wollte Rhodan wissen. Fast hätte er gefragt, ob man ihn dazu zwingen würde.
試訳:
「わたしに意識集合体に加わるよう……うながすつもりか?」あやうく言いかけたのだ。強制するつもりか、と。
まあ、ここは前後の文脈的に意味が逆転するようなこともないので、誤訳とまでは言わない。しかし、頭をよぎったどころか、喉元まで出かかり口ごもったのだ。
ハヤカワ版:
「これはなんなのだ? 駆動装置なのか?」
原文:
≫Was stellt das hier dar? Einen Transmitter?≪
試訳:
「これは何なのだ? 転送機かね?」
ここまでくると確信犯である。そこまで駆動装置にしたいのだろうか。まあ、そうしないと遡って修正しなくちゃならないので、駆動装置にしてしまいたいのだろう。きっと。
ハヤカワ版(p253):
われわれ、転換点にいるんです、ペリー」
原文:
Wir befinden uns in einer kritischen Situation, Perry.≪
試訳:
われわれ、危機的状況にあるんです、ペリー」
2004年私家版では“非常事態下にある”とした。
クリティカルな状況にある、ということで、転換点は必ずしも誤訳ではない。しかし、「一種の転換装置です」「エネルギーに転換しているんです」「われわれ、転換点にいるんです」と一連の会話でつづけたら、ローダンまでエネルギーに転換されてしまいそうである。もうちょい単語を選んでほしい。
#そもそも2個目の原語は beschaffen エネルギーを「調達する」である。わざとか。
ちょっとググって出てきた主立ったところで、危地、岐路、重大局面、限界状況……剣が峰、ピンチとゆーのもあった(笑) 選択肢はいくらでもある中で、一番わかりづらいの持ってきたよね。
#エデンIIはこれから天下分け目の大決戦をむかえるのです……と読むと、剣が峰がそれらしく見えてくるから不思議であるw
ハヤカワ版:
グレイの尖塔群からはなれるにつれ、それらは空気中に溶けるように見えなくなった。
原文:
Weiter entfernt von den Obelisken löste sich die graue Substanz in der Luft auf.
試訳:
オベリスクから離れるにつれ、グレイの霧は空中にかき消えた。
霧が晴れて、周囲の情景が見てとれるようになったのだ。この霧って、変換器稼働の副産物かな、となるわけなのだが。オベリスクが消えたら変換器動作不良になっちゃうから、見えなくなった、と補っている。
ハヤカワ版:
猫の背中のように丸くて低い建物
原語:
diesen buckelähnlich Erhebungen
試訳:
これらこぶ状の隆起
Buckel は『ノートルダムのせむし男』のように脊椎湾曲のため背中がこぶ状に見えたものを指し、これが日本語では差別用語とされたことで、同症状(病名:Kyphose)の別名“猫背”が当てはめられた。語源的にはラテン語Gibbusとされるように「凸形の、瘤の」で、辞書を見ても「こぶ」と書いてある。猫なのは日本だけである。
せめて「低い建物」「低い建物」のくどい連呼だけでもどーにかしてほしい。
ハヤカワ版(p255):
カクタとローダンを連れて部屋の中央へ向かう。
原文:
Zusammen mit Kakuta nahm er Rhodan in die Mitte.
試訳:
カクタとともに、ローダンをはさむような位置に立つ。
ローダンを中央に据えてカクタと向かい合った……かどうかまではわからないが、たぶんそうだろう。プロジェクション2名のあいだにはさむことで、ローダンの尻kもとい魂をひっこぬいたのだ。
ハヤカワ版(p256):
……あんなちいさなもののなかに。
原文:
– in einer derartigen Enge.
試訳:
――ああも窮屈なものの中で。
誤訳ではないのだが、この Enge(狭いところ)、ほぼおなじ表現がp266で出てくる。
ハヤカワ版:
押しやられるような感覚があり、それがすぐにはげしい衝撃にまで高まる。とてつもなくせまくるしい片すみに押し込まれたと思ったら、そこは自分の肉体のなかだった。
原文:
Rhodan spürte eine Berührung, die einem heftigen körperlichen Schlag gleichkam, dann wurde er in die im ersten Augenblick unerträgliche Enge gedrückt, die sein Körper war.
試訳:
殴られたような衝撃を感じるとともに、ローダンは耐えがたいほど窮屈なものに押し込められていた。それは、自分の肉体だった。
使用前・使用後じゃないけど、おなじものを、おなじように感じているわけだから、できるなら揃えておいた方が良いと思うのだ。
なお、動詞 gleichkommen は「~に等しい」。関係代名詞もあるし、高まっているわけではない。ボディブローにも等しい接触、である。
ハヤカワ版(p256):
数十億の意識がローダンに集中し、すべてを見通している。それは感動的であると同時に、打ちのめされる体験だった。
原文:
Milliarden Bewusstseine waren auf ihn konzentriert. Sie beobachteten ihn. Sie durchdrangen ihn. Es war erhebend und niederschmetternd zugleich.
試訳:
数十億の意識が彼に集中している。見つめられている。見透かされている。誇らしくもあると同時に打ちのめされる。
上げて、落とす、である。原文のリズムを考慮したらこんな感じに。
老人ホームへ慰問に訪れたら、じーちゃんばーちゃんに取り囲まれたの図。
ハヤカワ版(p257):
この力の集合体のすべてを一組織に結集し、確実に使命を遂行するために。
原文:
Es geht darum, diese Mächtigkeitsballung mit einer Organisation zu durchdringen, die ganz bestimmte Aufgaben zu erfüllen hat.
試訳:
ある特定の果たすべき使命をもつ組織で力の集合体を網羅するのだ。
すでに何回か述べているが、 bestimmt は「特定の、さだめられた」。
Es geht darum, ~ は、バルディオク裁判におけるケモアウクの弁論で解説した、「~が問題だ」である。この場合の“問題”すなわち前の文章で語られた計画(Unternehmen)のこと。なので訳としては、前の文章をうけて、「それは、すなわち」くらいと取っておけばいいだろう。
(→ また850話・バルディオク裁判)
ハヤカワ版(p261):
デスクの上を白紙だらけにしておくのが、かれの奇妙な癖だ。
原文:
Es ist eine Marotte von J. Chandler, seinen Schreibtisch mit diesem weißen, unschuldigen Papier zu bedecken.
試訳:
これはJ・チャンドラーの奇癖だった。デスクを、この白く無垢な紙で覆いかくすのは。
隠しているのは無垢(unschuldig)な白紙と正反対の罪(Schuld)の意識か――と、読者にストレートに想像させる材料を削る理由はなんだろうか。
◆
〈それ〉の展開する一大事業、コスミック・ハンザの構想に目を輝かせるローダン。しかも、堂々と“裏がある”と言い切るあたり、さすが超知性体である(笑)
エデンIIで非常事態宣言が出ている以上、ある程度予想がつくことではあるが、ハンザの裏の(真の)目的とは、敵対する超知性体セト=アポフィスの侵攻に対するみかじめ団体なわけだ。
では、〈それ〉とアポりんの双方が、なぜ現在のような抗争にいたったか……ということで、この宇宙における生命の進化というものに話がいたる。
すでに772話「フリノスの幽霊」においてケロスカーが、力の集合体と超知性体について、モデルを用いて解説しているように、フォルツ宇宙における生命の進化は同心円構造――たまねぎの皮になぞらえて表現される。たまねぎの中心は宇宙のはじまり以前の絶対の虚無で、以下外側へ向かって順に、
- 始原の混沌
- 無機物の皮(惑星、恒星、銀河の誕生)
- 有機物の皮(原始大洋における有機物のスープあたりまでか)
- 原始生命の皮(動植物、知性や社会構造を持たない)
- 知性体の皮(狩猟文化から工業文明まで含む)
- 宇宙航行の皮(太陽系帝国はこの段階)
- 多銀河連合体の皮(公会議はこの段階)
- 超知性体の皮(力の集合体の形成)
- 物質の泉/沼の皮(超知性体+力の集合体→存在形態の変化)
- コスモクラートの皮(詳細不明)
- 以降不詳
ただし、Perrypedia等を参照してもらえばわかるが、これは現行のモデルとはかなり異なっている。
草案作家をヴルチェクが務めた時代には、一時〈人の皮〉という、原始生命体から多銀河連合体まで含めた、この宇宙に生きる生命を一括する表現が用いられたが、これもまた過去のものとなっている。
おそらくは超知性体の〈核〉ないし〈アンカー〉という概念が登場したあたりからだろうか。この宇宙に存在する何かを破壊することがその超知性体にとって致命的な作用をもたらすわけだが、たとえば〈それ〉のように肉体を持たぬ超知性体であっても、〈核〉がこの宇宙――“精神的中心”だったり超空間だったりもするが――にある以上、結局のところ“こちら側”に生きる存在である、という考え方が主流となっていく。
近年ではこれを Leben an sich (生命そのもの)……ここでは〈生命総体〉と仮訳しておくが、コスモクラートのような〈彼岸〉に在る超越者たちとの対蹠的存在として表現する。そのため、現在の進化モデルでは超知性体までを含めて〈知性ある生命体の皮〉と位置づけているのだ。
余談ついでにいっておくと、本書でもローダンがちらりと漏らす“たまねぎモデルの一番外の皮”のことを、最近では“〈法〉の地平線”と表現している。異なる時間線の話になるが、「他にも存在する究極の三謎」の内容なので、はたしていつか本編のネタに取りあげられるかもわからないことではあるのだが(笑)
閑話休題。
とにかく、進化の道程を、上記モデルのように歩んでいけるか否かには、一点、明確とは言いがたい基準が存在する。ポジティヴか、ネガティヴか、である。
アポりんの進化史(昔話)を読むと、彼女はその時点で入手しえた手段を活用して、ひたすら上昇志向を満たしていく。それがネガティヴとされるのは、この進化モデルが一種の“倫理コード”にしたがっているからなのだが……その“ものさし”が普遍的なものであるかは、現状ではわからないのだ。
◆
ハヤカワ版(p262):
生きているあいだにセト=アポフィスからじかに任命されることは、断じてない。その必要もないから。つまり、協力者は生涯、自分がセト=アポフィスの奴隷だったと知らないことになる。
原文:
Es kommt vor, dass Seth-Apophis einen Helfer während seines gesamten Lebens überhaupt nicht einsetzt, weil keine Notwendigkeit dazu besteht. Ein solches Wesen stirbt, ohne jemals zu erfahren, dass es ein potentieller Sklave von Seth-Apophis war.
試訳:
協力者によっては、必要が生じなければ、生涯動員されないこともありうるのだ。そうした存在は、自分がセト=アポフィスの潜在的奴隷であったことを知ることもないまま終わる。
「必要性がないからと、ある奴隷(協力者)を生涯投入しないこともある」と、すぱっと直訳した方がわかりやすいかもしれない。というか、セト=アポフィスの奴隷とは、無自覚な“草”だから、“潜在的”という言葉を削除していなければ、絶対違和感があるはずなのだ、この訳文。
動詞 einsetzen にはたしかに「任命する、設定する」という意味もあるが、ローダンでは一般的に「(労働力、戦力を)投入する、動員する」である。手元の新現代独和辞典では後者の方が先にくるし、読む本が偏っているせいか、私的にはこれまで前者の例に遭遇したことがないなぁ。
ハヤカワ版(p263):
セト=アポフィスの運命に介入するのはかんたんなことではないが、
原文:
Es ist unwahrscheinlich, dass wir das Schicksal von Seth-Apophis günstig beeinflussen können,
試訳:
セト=アポフィスの運命を好転させることはほとんど不可能だが、
günstig 「好都合な、有利な」……というと、アポりんの運命をこっちの都合がいいようにいじくりまわすようだが(笑) 好天とかにも使用する形容詞なので、運命を良い方向へ導く影響をあたえる、くらいに取っておくべきだろう。
……まあ、実際不可能だったわけだが(爆)
ハヤカワ版:
かれらはセト=アポフィスとわたしの力の集合体のあいだにある、緩衝地帯のひとつなのだ。
原文:
Sie sind dabei, eine Pufferzone zwischen den Mächtigkeitsballungen von Seth-Apophis und der meinen aufzubauen.
試訳:
彼らはセト=アポフィスとわたしの力の球形体の狭間に緩衝地帯を築こうとしている。
dabei は「(空間的に)そばにいる」「(時間的に)その時に、同時に、~しようとしている」。
ハヤカワ版は前者として読んだようだが、そのために動詞 aufbauen 「建設する」を無視している。その後のハヤカワ版を読んだ方なら、この文章の意味するところが、アトランと《ソル》によるクラン帝国建設(1000話時点では未来の話)であることはおわかりだろう。
……そもそも、コスモクラートが緩衝地帯って、泉の彼岸をどう考えているのかな?
ハヤカワ版(p264):
〈ほとんどの存在形態が、これらの段階のどこかに位置している。
原文:
≫Die meisten Existenzformen bleiben irgendwo an dieser Stelle hängen≪,
試訳:
〈たいていの存在は、このあたりで行き詰まる〉
分離動詞 hängenbleiben 「ぶら下がる、ひっかかる、(ひっかかって)動かない」。
場所、を意味する Stelle も単数なので、あくまでこの位置(皮)で、なのだ。
ハヤカワ版(p266):
おお! やっとわかった。
なんということがわかってしまったのか。
原文:
Mein Gott!, dachte Rhodan. Nun verstehe ich auch das.
Und wie ich es verstehe.
試訳:
神よ! いまのわたしは、それも理解している。
いやというほど、理解している。
ここ、地の文だけど現在形なので、ローダンの思考がダダ漏れている感じか(笑)
この前にあたる“理解”は2万年の区切りについてで、この文章では“精神を肉体の絆から開放できることをよろこぶようになる”についての理解。どれほど(英:how)わたしは理解していることか、が直訳。
ここは今わかったというより、エデンIIへ跳躍する前にすでに自覚している。誤訳というか、気分の問題ではある。私家版は〈それ〉のセリフも「ようやく理解してくれたな」としているので、そっちに揃えたもの。
先読みしていると、ローダンのことを“敬虔なキリスト者(だった)”とする表現をたまに見かけるのだが、ハヤカワ版にはあまりそういうイメージがない。松谷先生もそのへんは意訳していたのか、そもそも当時はあまりそういう描写がなかったのか。実際わたしも、私家版では「なんということだ!」と訳してるし >Mein Gott
……それとも単にわたしの記憶力が悪いのかorz
ハヤカワ版(p269):
こちらに注意を向ける余裕がなさそうだ、と、ローダンが思いはじめたとき、ようやく“それ”の声が届いた。
原文:
Rhodan hatte den Eindruck, dass ES sich schwer auf ihn konzentrieren konnte, als es schließlich wieder in mentalen Kontakt zu ihm trat.
試訳:
ようやくメンタル・コンタクトが成立しても、ローダンの感触では、〈それ〉はこちらに集中するのが難しそうだった。
文章の主客が転倒している。まあ、文章をアタマから訳すこと自体は悪くないのだけど。
おいおい、話すときには人の目を見て話しなさい、である。
ハヤカワ版:
超越知性体はつねに力の集合体の安定と拡張に意を注いでいる。
原文:
Eine Superintelligenz wird stets bemüht sein, ihre Mächtigkeitsballung zu stabilisieren und auszubauen. Dazu bedarf es unvorstellbarer geistiger Anstrengungen.
試訳:
超知性体はつねに力の集合体を安定させ、拡大しようと努める。それには想像を絶する精神的労力が必要だ。
意を注いでる、で次の文章まで含めちゃったのかな。
消えた〈それ〉のセリフ、なんだか言い訳くさくて笑えるのだがw
ハヤカワ版:
ネガティヴな力が優勢になれば、力の集合体は崩壊する〉
〈セト=アポフィスの力の集合体がそうなりかかっていると?〉
原文:
Sobald negative Kräfte die Oberhand gewinnen, beginnt eine Mächtigkeitsballung in sich zusammenzustürzen.≪
≫Das ist das Schicksal, das Seth-Apophis droht?≪
試訳:
ネガティヴな力が優位を占めると、力の集合体は崩壊をはじめる」
「それがセト=アポフィスを脅かす運命なのですね?」
p263で話題にのぼった、アポりんの好転させるべき運命の話である。
ハヤカワ版(p270):
そのあとにとらえた心理性の背景音を思いだす。ジャルミタラという精神存在のことも、物質の窪地に行ったハルノから聞いた。
原文:
Im nachhinein erinnerte er sich an ein mentales Hintergrundrauschen, das er damals empfangen hatte. Er hatte es einer psychischen Existenz zugeschrieben, die sich Jarmithara genannt hatte.
試訳:
いまにして思えば、当時とらえたメンタル背景音。あれはジャルミタラという精神存在によると考えたものだが。
Im nachhinein は「後からの、追加の」Wiktionary等参照すると「すべて終わった時点では」。
ジャルミタラの名前自体は、たしかにハルノから伝え聞いたものなのだろうが、この追加の作文だとメンタル背景音とジャルミタラがイコールでつながらない。
ハヤカワ版(p271):
また同時に、さらなる進化を遂げた超越知性体の内部には、泉の彼岸へ至る門が形成されるのだ〉
原文:
Die weiterentwickelten Superintelligenzen bilden in ihrer neuen Daseinsform gleichzeitig Tore auf die andere Seite.≪
試訳:
さらなる進化を遂げた超知性体は、その新たな存在形態の内に、同時に彼岸への門を形成するのだ〉
門が形成されるから、エネルギーが流入してくる、というのがこの段落の主旨。この時点では、解説はまだコスモクラートには到達していない。
なんだか、あちらでもこちらでも“(新たな)存在形態”という単語を削除しているけど、超知性体の新たな存在形態=物質の泉で、それはすでに超知性体ではない。
ハヤカワ版:
物質の泉の段階を過ぎると……やがて超越知性体はある存在というか、勢力に進化する。
原文:
Irgendwann endet auch der Zustand der Materiequelle – sie wird zu einem Wesen oder zu einer Macht, die wir unter dem Begriff >Kosmokraten< kennen.
試訳:
物質の泉の段階も、いつかは終わる――われわれが“コスモクラート”の概念で知る存在、あるいは力に変わるのだ。
前項の“すでに超知性体ではない”がわかっていないから、こういう訳文になる。主語 sie は、物質の泉である。
あと、力 Macht が複数集まるから勢力 Mächte なのだ。
ハヤカワ版(p273):
それこそ深遠な宇宙的意味
原文:
also einen tiefen kosmologischen Sinn
試訳:
つまり深遠な宇宙論的意味
深淵の騎士(Ritter der Tiefe)との語呂合わせと取った訳はおみごと(笑)
ハヤカワ版:
いずれは物質の泉となる力の集合体を形成するため、争いに参加することを要請されている。
原文:
und sie war aufgerufen, das Ihrige dazu beizutragen, um eine Mächtigkeitsballung zu erhalten, die einmal eine Materiequelle werden sollte.
試訳:
いつか物質の泉たるべき力の集合体の維持に、彼らなりの役目をはたすために召集されたのだ。
ここでいう「ある(ひとつの)力の集合体」とは〈それ〉のもの。
そもそも〈それ〉は語らないが、実は超知性体が力の集合体ごと物質の泉になる、という表現は、銀河系を含む局部銀河群壊滅を意味している……かもしれないのだ。そのあたりは、色々と論議の的であったのだが、2899話において、あるネガティヴ超知性体は勢力圏である銀河を呑み込んで物質の沼へと変じた。テラナーが超知性体へといたる道は遠く険しい(ぁ
ハヤカワ版(p274):
〈この知識を人類に伝えるのは困難だろう。たとえほかの者に話したとしても、まず理解されない。だから宇宙ハンザは、その背景に深い意味を持つものとして創設する必要がある。この組織に正しく息を吹きこめないかぎり、目的を達することはできない。
原文:
≫Du wirst schwer an diesem Wissen zu tragen haben≪, prophezeite ES. ≫Auch wenn du es mit anderen Menschen teilst, wird man dich nur in seltenen Fällen verstehen. Es liegt also an dir, die Kosmische Hanse so aufzubauen, dass sie einen tieferen Sinn bekommt. Als eine Organisation, der man kein Leben einhaucht, wird sie ihre Aufgabe kaum erfullen können.
試訳:
〈この知識は、きっと重荷になるだろう〉と、〈それ〉が予言する。〈たとえ誰かと分かち合っても、理解が得られるのはごく稀なケースだ。したがって、コスミック・ハンザがより深遠な意味を持つよう組織することは、ひとえにきみの双肩にかかっている。生命が吹きこまれていない組織には、その使命をはたすことなどできない。
これまでのネタは、基本的に、キミだけに宛てたものなんだよ、である。だから裏の目的の件については、キミにまかせたからね? である。
通商組織としてのガワだけつくっても、真相を知らないメンツではアポりんの攻撃に対処できないのだ。組織に魂を吹きこむ匠の技を要求されたローダン、その肝心の“キミ”がハヤカワ版からは削除されている。防衛失敗である(笑)
ハヤカワ版(p283):
人間がカオス的宇宙に偶然うまれたものではないことを信じている。
だれもが心の奥におさえきれない熱望を秘めていることを信じている。人類の宇宙的な運命を知りたいという熱望を。
人類が崖っぷちから身を投げて、自分たちが荒廃させた大地に落下することはないと、信じている。
人類がすばらしい宇宙の一角を占め、そこで調和に満ちて生きていくと信じている。
原文:
Er glaubt nicht, dass der Mensch ein Produkt des Zufalls in einem chaotischen Kosmos ist.
Er glaubt, dass tief in jedem Menschen eine unstillbare Sehnsucht verankert ist, seine kosmische Bestimmung zu erfahren.
Er glaubt nicht, dass der Mensch über den Rand des Abgrunds hinaustaumeln und auf einer von ihm selbst verwüsteten Erde untergehen wird.
Er glaubt, dass der Mensch sich als Teil eines wunderbaren Universums begreifen und voller Harmonie darin leben kann.
試訳:
人間が渾沌とした宇宙における偶然の産物だとは思わない。
人間ひとりひとりの奥深く、おのが天命を知ることをもとめてやまない気持ちが根ざすと信じている。
人類が奈落のふちを踏みはずし、地球もろとも自滅するとは思わない。
人類が自らをこのすばらしき大宇宙の一部と知り、調和に満ちて生きていけると信じている。
原文の glaubt nicht / glaubt / glaubt nicht / glaubt のリズム、ガン無視である。まあ、百歩譲ってそれはいいとしよう。
動詞 untergehen は「(日が、天体が)沈む」「没落する、滅ぶ」で、人が落下する意味はない。Erde(英:earth)は女性名詞なので auf+III格は方向ではなく場所で、「自らが荒廃させた大地(地球)で(人類が)滅ぶ」。核のボタン押したりしないさー、だ。
また、最後の文章は、ペリー少年が宇宙への窓を見せられて「調和のとれた光の波の一部」と感じた、あれとまったく同じことである。一角を占め、とか、なに領土主義に陥ってるんだと言いたい。
最後の最後、決めの文章でこんな誤訳してどーするの。
ハヤカワ版(p285):
10 テラニア百科事典の記述
原文:
10. Encyclopaedia Terrania
試訳:
10 エンサイクロペディア・テラニア
これまで何度もシリーズに登場した百科事典の名称である。ぜひ踏襲していただきたい。
◆
ここに、ペリー・ローダンの長かった旅路が終わり、新たな使命を携えてテラへと帰還する。
純粋なテラナーの消失とともに、その夢も失われたかに思われたローダンだが、人類のみならず、銀河系諸種族と一体となって超知性体への道を歩むという、新しいお題目によって息を吹きかえす。
〈それ〉によって開陳された、ポジティヴな生命が歩む秩序立った進化の道筋。そこを歩む、それこそが彼の新しい“天命”と思われた……。
まあ、この先のストーリーとか知っていると、なんとまあ純朴な、と呆れたくなる向きもあろう(笑) 実際、後にローダンが知る〈究極の謎〉のカラクリは、コスモクラートが低次の生命体である彼を、まさに“道具”として使い潰す気満々であったことを示している。
1100話「フロストルービン」を経由して、1200話「オルドバン」へと、セト=アポフィスとの戦いと並行して、究極の謎を解くためのヴィールスインペリウムの再建計画と〈ヴィシュナ〉の覚醒、“トリイクレ=9”を奪回するため出現した〈無限アルマダ〉、さらに〈エレメントの十戒〉の参戦と、目まぐるしく展開するフォルツ・ストーリーは、おそらく“その先”に何かをめざしていたのだと思う。その紡がれることがなかったのは、フォルツ・ファンとしては無念の一言に尽きる。
ただ、フォルツが残した1209話までの草案は、ローダンによるクロノフォシルの活性化と、アトランらによる〈深淵の地〉の下準備、その両方の端緒までが用意されているので、その行き着く先――1272話「騎士たちの叛逆」までの大筋は、おそらくすでに詰めてあったのだと思われる。
実際にできあがった形が、フォルツの構想をヴルチェクらが活かしきったか、独自のアイデアで上書きしたのかはこれもまた明らかではないが……そこでまた、すべてを失うローダンに、フォルツはどんな“第三の道”を歩ませるつもりであったのだろうか。
◆
「最終回 人類の天命の物語」に続く。
最後は、本書のテーマとは何か。フォルツが訴えたかったのはどんなことか、考察してみたいと思う。ただし、ノリはいつものごやてんである。