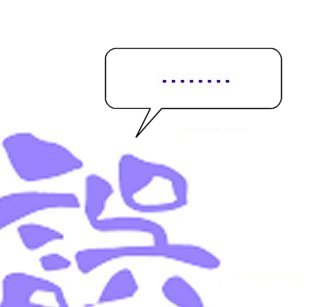Batterie der Bildschirme /
ずらり並んだスクリーン
びびびびび、というと、水木先生の漫画で往復ビンタが吹き荒れるシーンを思い出すわけだが。
バッテリー、という単語を見ると、やっぱり電池を連想してしまう。モニターの電源? なんか脈絡がないのだが……と思ったら、ずらっと並んだものを意味する慣用句だった。とはいえ、どちらもクナイフェル作品である『恒星三角形の呪縛』と今回の『時間ダイヴァー』、まだ2回しか遭遇していないのだけれど。
語源を調べてみると、バッテリーという語、元々は「殴る、打つ」という意味のラテン語battuereに由来するらしい。野球のバッテリーとか、軍事用語のバタリオンとかも同根。大砲がずらっと並んだイメージであるようだ。
だから、電池→びびびびび→往復ビンタ、という連想は、実は正しかったりする(をひ
冗談はさておき、じゃあなぜ電池がバッテリーかというと、フランクリンが凧を揚げて雷と電気の関係を実証した実験の際、ライデン瓶がずらっと並んでいたから……ということらしい。
ボルタ電池が銅と亜鉛をメガマックのように幾重にも積みかさねた様からきたわけではない、みたい。あれはあれで、すらっと並んでいるように思うのだけど(笑)
前回(恒星三角)のときは、「へぇ、そんな意味もあるのかね」と、辞書を読み流しただけだったのだが、とんだ物知らずであった。いやはや。